認知症いろいろ・自律神経もいろいろ

~ボリヴェーガル理論にふれて~
最近、体調を崩してしまいました。夜になると高熱が出て、ひどい汗。持病もあるので、いろいろ検査をしましたが、原因は見つからず「不明熱」という診断。幸い、今は熱も治まり、落ち着いています。なんだったのだろう?そんな疑問を抱えていたとき、ふと参加していたサロンで、自律神経の話題が出ました。これがヒントになり、自分でも本を手に取ってみました。そして出会ったのが、「ポリヴェーガル理論」という考え方です。
赤=交感神経
まず、「赤=交感神経」は、危険に立ち向かうためのエネルギー。
怒り、焦り、不安、暴力的な行動など、BPSD(認知症の行動・心理症状)の陽性症状ととてもよく似ています。
このとき、身体は心拍数が上がり、呼吸も浅く速くなっています。
まさに、戦闘モードです。
青=背側迷走神経複合体
次に、「青=背側迷走神経複合体」は、ブレーキを踏む働き。
危険を感じると、身体が固まり、動けなくなり、心も閉じてしまう。
無気力、無感動、傾眠といったBPSDの陰性症状がここに当たります。
まるでエネルギーが一気にシャットダウンしたような状態です。
緑=腹側迷走神経複合体
では、どうすればいいのか?
ヒントは「緑=腹側迷走神経複合体」にあります。
ここは、安全を感じたときに働く神経です。
安心感、信頼感、穏やかさ、喜び― 人が人らしく、穏やかに過ごせるための大切な感覚。
この「緑」の状態を作り出すことが、ケアのカギになると感じました。
まとめ
自律神経は自分の意志ではコントロールできません。
でも、周りの環境を整えることで、「赤」や「青」に偏ることを減らし、「緑」を育てることができるかもしれない。
認知症ケアも同じ。
安心できる空間、安全な関係性、信頼できるスタッフ─
そんな「緑」を意識していくことで、症状の悪化を防ぐ一助になるのではないかと思っています。
まだまだ学びの途中ですが、これからも実践を重ねながら、またご報告していきたいと思います。
もし興味がある方がいれば、一緒に学んでいきませんか?
(参考:『ポリヴェーガル理論がやさしくわかる本』吉里恒昭先生著)
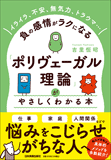

日本認知症研究会副代表。看護学校卒業後、内科外来、透析室勤務を経て訪問看護ステーションにて3年間在宅医療に関わり、その後、介護付き有料老人ホームの看護職員として長年務められる。多くの認知症の入居者に携わるうちに、認知症について興味を持ち看護師として貢献できる認知症ケアについて学ばれる。周囲の仲間からは「大将」の愛称で親しまれ、医師主体の研究会の代表を務められた他、中国、イタリアで開催された学会でのご講演など多方面で活躍されている。
